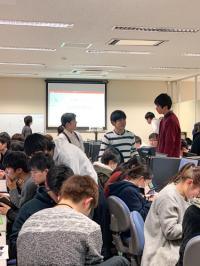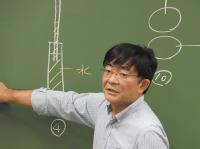2018.07.06
先日、学内の各所で行われた
環境マネジメントシステム監査。
本学では、環境保全、省エネ、など、
全学の構成員がそれぞれの立場から積極的に取り組んで、
環境にやさしい「エコ大学」を目指しています。
その「意識して取り組むための道しるべ」のひとつとして、
「環境マネジメントマニュアル」が作られていたり
それに沿った取り組みができるよう
年に一度のこの監査が全学をあげて行われていたりします。
この土台たちがあるからこそ、教職員、学生さん、すべての構成員が
ごみや実験廃棄物の分別、再利用できる資源の回収や省エネなど
それぞれにできることを具体的に取り組みやすくなっています。
そのシステムが適切に運用されているか、
本学の全構成員が環境のためにやるべきことを把握できているか。
それを学内の監査員と学生さんとで見極めるべく
各部局や学部をチェックする、年に一度の監査の日。
(学生さんは「環境マネジメント実践学」の授業の一環として参加します)

この日は「正式な場なのでそれなりの身なりを」とのことで
学生さんもスーツ着用(クールビズ)です。
就活やインターンシップ以外でスーツを着る機会、
こんなところにあるんですね。
その服装もあいまって、まだ開始前なのにこの厳かな雰囲気、
ちょっと萎縮しちゃいそうです。
でも、違う見方をすれば、
監査する側もされる側もそれくらい真剣に取り組んでいるということ。
また、
省エネ=徹底的に削減
というだけの考えになってしまうと
場合によっては熱中症や脱水など健康を損ねる事もあるし、
大事な研究や実験で使う試料や試薬などのためには
必要な機器や装置はある程度の資源を使っても
しっかり稼動させなければならず。
ひとことで「エコ」「環境に配慮」といっても
さまざまな面から考えていかなければなりません。
だからこそ、こうやってヒアリングや現場確認をおこなって
その時その状況に最適化されているかを
定期的にお互いに確認しながら取り組んでいくのが
大切なのかもしれませんね。

場所は変わり、
農学部一年生の実習は、そろそろ収穫モードに移りつつあります。

ここまで大きくなると、さすがにかぶりつく猛者はいないんですね…。

持ち帰りをどうするのか、協議が長引いている模様。
大きさが大きさですし、数も数ですしね…。

ここだけでなく、
あちこちでダイコンの山を囲んでミーティングが開催されています。
「おろし金って100均に売ってるっけ?」
なんて会話が聞こえてきたり。
おろしで肉や魚をさっぱりいただくのが
量的にもこなせるし季節柄的にもおいしくいただけそう。
電車やバスで通学する学生さんはちょっと帰り道が大変そうです。
ただ、これはまだ序の口。
実習最終回にはじゃがいもが控えていますので…。
「収穫物持ち返り用のビニール袋を持参するように」と言われて、
厚くて大きい丈夫なスーパーの袋ではなく
コンビニでジュースとガムを買った時ぐらいの
薄くて小さな袋を持ってくる学生さんが後を絶たないので、
「このダイコンで、野菜の収穫量の目安を理解してくれてたら良いな…」
なんてひっそりと願うわたしです。
「エコ」「環境」のお話と通ずるのですが…
最近のスーパーのレジ袋は省資源のために薄手のものが多くて
大型の野菜を入れたら重みで破けることもあるので、
こういう実習の持ち帰り袋もエコバッグのように丈夫で再利用できるものが
そのうち推奨されるようになってくるのかなぁ、
…なんて今日のふたつの話題を通してふと思う週末です。